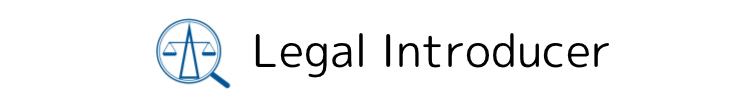| Point |
| 1.不作為犯の因果関係はどのような場合に認められるか |
1.事案の概要
被告人は、ホテルで被害者(13歳)の左腕に覚せい剤を含有する水溶液を注射しました。すると、被害者は頭痛・吐き気等の症状を訴え始め、その後錯乱状態になり重篤な状態に陥りました。しかし、被告人は、医師を呼んだりホテル従業員に知らせたりすることなく、その場を立ち去りました。その後、被害者は死亡しました。
(関連条文)
・刑法218条 「老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、3月以上5年以下の懲役に処する。」
・刑法219条 「前2条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する」
【争点】
・被告人の不作為と結果との間に因果関係はあるか。
2.判旨と解説
本件では、被告人が被害者を放置して立ち去った行為と、被害者の死との間に因果関係が認められるかが問題となりました。なお、被告人には殺意はないため不作為による殺人罪は問題となりません。また、被告人の行為と被害者の死との間に因果関係が否定された場合、被告人には保護責任者遺棄等罪が成立するにとどまります。
*殺人罪の説明はこちら
*故意の解説はこちら
*保護責任者遺棄等罪の説明はこちら
判例によれば、因果関係の判断は、条件関係を前提に、実行行為の有する危険性が結果へと現実化したか否かを基準に行われます。
*因果関係の説明はこちら
まず本件では、被告人の保護責任者性が問題になります。この判断は、不真正不作為犯の作為義務と同一あるいはほぼ同一と考えられています。本件では、被害者の錯乱状態は、被告人による覚せい剤の投与により生じています。また、事件が起こった現場は、ホテルの室内であったため、被告人以外に被害者の救助を期待できない状況でした。そのため、被告人に保護責任者たる地位が認められます。
*不作為犯の説明はこちら
次に、条件関係が問題となります。もっとも、本件では、被告人の実行行為は不作為です。そのため、実行行為がなければ結果は発生していなかったか、といった判断手法は、そのままでは使えません。
そこで、最高裁は、期待された行為をしていれば、結果を回避できたことが、合理的な疑いを超える程度に確実であったか、といった基準を用いて因果関係を判断します。
まず、条件関係について判断します。本件では、被害者が若く、また、特段の疾病もなかったことから、被告人が期待された行為(救急医療の要請)をしていれば被害者の救命が十中八九可能であったと言えます。そうすると、被害者の救命は合理的な疑いを超える程度に確実であったと言え、被告人の不作為と被害者の死亡という結果との間に条件関係が認められます。
次に、実行行為の有する危険性が結果へと現実化したかが問題となります*
本件では、被害者が重篤状態にあり、また場所はホテルの客室内で被告人の他に人がいませんでした。そのため、被害者の救護を被告人の他に期待できない状況にありました。そうすると、被告人がその場を立ち去ることは、被害者を死亡させる危険性を有する行為と評価できます。そして、実際に被告人が立ち去った結果、被害者は死亡するに至っているので、実行行為の有する危険が結果へと現実化したと言えます。
したがって、被告人の実行行為と結果との間に因果関係が認められ、被告人に保護責任者遺棄致死罪が成立します。
| *なお、本件で最高裁はこの点について検討していません。この点、条件関係と危険の現実化の判断は、不作為犯においては≒のケースが多く、本件もそのような場合に当たることが1つの理由だと思わます。ただ、条件関係が認められても、実行行為の危険性が現実化していないと判断されるケースも存在しうるでしょう。 たとえば、本件で被害者は、被告人の立ち去りの後に侵入してきた者により射殺された、という事実が認定されたとします。この場合、被告人の行為と結果に条件関係はあります(立ち去らず被害者を病院に連れてくなどしていれば、ほぼ確実に被害者は助かったため)。他方で、細かな事実関係を設定する必要はありますが、この場合、実行行為の危険が現実化したとは、言えないと判断されることが多いでしょう。 |
↓原文
「原判決の認定によれば、被害者の女性が被告人らによって注射された覚せい剤により錯乱状態に陥った午前零時半ころの時点において、直ちに被告人が救急医療を要請していれば、同女が年若く(当時一三年)、生命力が旺盛で、特段の疾病がなかったことなどから、十中八九同女の救命が可能であったというのである。そうすると、同女の救命は合理的な疑いを超える程度に確実であったと認められるから、被告人がこのような措置をとることなく漫然と同女をホテル客室に放置した行為と午前二時一五分ころから午前四時ころまでの間に同女が同室で覚せい剤による急性心不全のため死亡した結果との間には、刑法上の因果関係があると認めるのが相当である。したがって、原判決がこれと同旨の判断に立ち、保護者遺棄致死罪の成立を認めたのは、正当である。」
*大阪南港事件の解説はこちら
*スキューバダイビング事件の解説はこちら
*トランク事件の解説はこちら