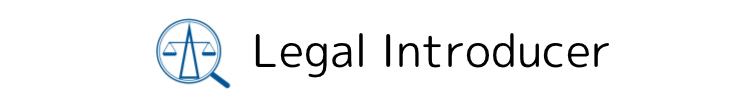| Point |
| 1.本件事実関係によれば、被害者に本件ポシェットの占有が認められ、被告人に窃盗罪が成立する。 |
1.事案の概要
被害者は、公園でベンチに座り、傍らに自身のポシェット(以下「本件ポシェット」と
いう。)を置いて友人と話をしていました。その後、被害者は本件ポシェットをベンチ上に置き忘れたまま、友人と共にその場を離れました。被告人は、被害者らが公園出口にある横断歩道橋を上り、上記ベンチから約27mの距離にあるその階段踊り場まで行ったのを見たとき、自身の周りに人もいなかったことから、今だと思って本件ポシェットを取り上げました。そして、それを持ってその場を離れ,公園内の公衆トイレ内に入り,本件ポシェットを開けて中から現金を抜き取りました。被害者は、上記歩道橋を渡り約200m離れた私鉄駅の改札口付近まで2分ほど歩いたところで、本件ポシェットを置き忘れたことに気付き、上記ベンチの所まで走って戻ったものの、既に本件ポシェットは無くなっていました。
(関連条文)
・刑法235条 「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
・刑法254条 「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。」
【争点】
・本件ポシェットに対する被害者の占有は認められるか
2.判旨と解説
本件では、被告人が本件ポシェットを取り上げた時点で、被害者に本件ポシェットに対する占有があったか否かが問題となりました。被害者による占有が認められた場合には窃盗罪が、占有が認められなかった場合には占有離脱物横領罪が問題となります。
*窃盗罪の解説はこちら
被害者が本件ポシェットの置忘れに気づいたのは駅改札口です。しかし、被告人が本件ポシェットを取り上げたのは、被害者がベンチから約27メートル離れた時点です。そのため被害者による占有の有無は、この時点を基準に判断しなければなりません。
27メートルは非常に近接した距離と言えるので、たとえ被害者が本件ポシェットのことを忘れていたとしても、これに対する占有を肯定できるでしょう。最高裁は、被告人に窃盗罪の成立を認めた原判断を是認しました。
「被告人が本件ポシェットを領得したのは,被害者がこれを置き忘れてベンチから約27mしか離れていない場所まで歩いて行った時点であったことなど本件の事実関係の下では,その時点において,被害者が本件ポシェットのことを一時的に失念したまま現場から立ち去りつつあったことを考慮しても,被害者の本件ポシェットに対する占有はなお失われておらず,被告人の本件領得行為は窃盗罪に当たるというべきであるから,原判断は結論において正当である。」